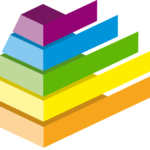こんにちは、天乃 繭です。
目次
認知症ってどんな病気なの?

でも、認知症について知ることによって、いい方向にお互いが向くことができると思うのよ

そうですよね、認知症も心臓病や脳梗塞、ガンなどと同じように『病気』の一つなんですが、なかなかそうは思えず、対応が遅れたり心ない言葉を言ってしまったりするんですよね。
私もそうでした。
でも、認知症がどういうものなのか、どのような症状が出てくるのか、認知症と診断された本人の気持ちは、っていうことに少しでも知識をもっていれば、イライラしたり傷つけたり傷ついたりすることも減っていくと思うのです。
イライラすることはとっても体力を消耗するし、そのストレスによって自分の身体も様々な影響を受けて、もしかしたら健康を害してしまっているかもしれないのです。
私の場合には、髪の毛が抜け落ちて、後頭部の、髪の表面ではなく中のほうがハゲてごっそりとなくなってしまって。。。。
後ろから風吹かないで~、エスカレーターで私の後ろに立たないで~、立っている人に見られてしまうから電車で座れな~い、など薄毛で悩んでいる男の人の気持ちがこの時ばかりはすご~くわかってしまいました。
このまま生えてこなかったらどーしよー!って真剣に悩み、皮膚科に相談に行ったりもしたんですよ。
半年から1年かけて元に戻りましたが、皮膚科の先生いわく、また抜けるっていうことを繰り返すかもしれないと・・・・
どーかもう抜けてハゲたりしませんよーに!! (ちょっと余談でした)
スポンサーリンク
とにかく、イライラしたり怒ったりしながら接すると、介護される人は、その理由がわからないので益々混乱して色々な困った行動に出てしまうんです。
そうなるともう負のスパイラルですよね。
介護する人もされる人もプラスになることは一つもなく、負の要素ばかりを積み上げていってしまうことになります。
とは言っても、私の経験上、矛盾するような言い方になってしまいますが、認知症の知識を多少もって相対したとしても、なかなかその知識を活かすことはできず、我慢の限界で怒鳴ってしまうことも多々あるかもしれません。
でもこれは仕方のないことです。
その気持ち、よくわかります。
でも、認知症に対する知識が全くないのと、ほんの少しでもあるのとでは全然違うと思うんです。
認知症についてちょっとでも知っていれば、例えその時は感情に負けてひどいことを言ってしまったとしても、この次は気を付けよう、あんな言い方をして悪かったな、と思えるようになります。
その思いは、直接言葉にしなくても、家族であれば必ず通じているはずです。
認知症の知識を身に付けてうまく対応できるに越したことはありませんが、うまくできなかったからと言って決して自分を責めることなく、今の状況を少しずつ少しずつ受け入れていくことができればいいんじゃないでしょうか。
私はそう思います。
だって、元気だった頃の親の姿がいつまでも自分達の中にはあるから、認知症になってしまった今の親の状態を受け入れるのはそう簡単なことではないのだから。
全てを受け入れていくことは並大抵のことではなく、たくさんの時間がかかると思います。
先の見えない真っ暗な洞窟の中にいる感じでいると思いますが、必ず光が見えてきます。
焦らず、少しずつ分かってあげながら見守っていきたいですよね。
認知症とは?
認知症に関する医学的な難しいことはわかりませんが、母が認知症と診断されてから私なりに調べてわかったことを書きたいと思います。
認知症とは、
脳の神経細胞が壊れて死滅したり、働きが悪くなることによって、様々な障害が起こり、
記憶が失われたり、時間や場所や人物などがわからなくなって生活に支障をきたす状態
です。
認知症の症状とは?
認知症には、アルツハイマーやレビー小体、血管性などの代表的なものは皆さんも知っての通りで、その症状は種類によって様々なのですが、どの種類の認知症かに関わらず、認知症全体に言える症状が大別して2つあります。
それは、
- 中核症状
- 周辺症状
です。

認知症には症状としてこの2つがあることを知るだけでも介護は随分と変わってくると思うのよ

では、もう少し詳しく見ていきましょう。
中核症状
中核症状とは、
脳の神経細胞が壊れてうまく働かなくなることによって起こり、残念ながら症状の進行を止めることは難しいと言われています。
そしてその中核症状には以下のような症状があります。
- 記憶障害
- 見当識障害
- 判断力障害
- 認知機能障害
<記憶障害とは>
初 期:数分前~数日前迄の記憶がなくなる
中 期:数ヶ月~1・2年前の記憶が抜ける
後 期:一部の過去の記憶を除いてほとんどの記憶がなくなる
<見当識障害とは>
『時間』 ⇒ 『場所』 ⇒ 『人物』 の順に、これらを記憶したり認識したりする能力が低下し、判別できなくなる
<判断力障害とは>
筋道を立てて考えたり計画したりすることができなくなり、判断力が低下していく
<認知機能障害とは>
- 言語障害
『読む』『書く』『聞く』『話す』などの能力が低下する - 行為障害
『飲み込む』『歩く』などの動作能力が低下、物の形や空間の認識ができない、人の動作のマネができない、今まで使ってきた道具の使い方がわからない、洋服の着方がわからないなど - 認識障害
目・耳・鼻・口から入ってくる情報を脳が認識できない - 実行機能障害
計画を立てる・順序立てる・組織化するなどの機能が低下する
周辺症状
周辺症状とは、
脳の機能低下(=中核症状)によって日常生活に混乱が生じ、そのことによって出てくる症状で、ケアや対応次第でその症状が緩和したり減らしたりすることができると言われています。
- 睡眠障害
- 幻覚や妄想
- 大声で叫ぶ
- 口数が多くなる、動き回る
- 徘徊
- 過食や拒食
- 暴力
- 不安や焦燥
- 人格変化
- 抑うつ
- 不潔行為 などなど
スポンサーリンク
まとめ
認知症の症状には大別して2つあります。
それは、
- 中核症状
- 周辺症状
です。
中核症状は、いったん認知症を発症すると、その段階によって症状が徐々に出てきてしまい、残念ながらその進行を止めることはできないと言われています。
一方、周辺症状は、その人の置かれている環境などによって様々な症状として現れてきますが、対応次第ではその症状を緩和・軽減することが可能と言われています。
介護をしている人は、『中核症状』以上にこの『周辺症状』によって振り回されるケースが多く、よくない対応をしてしまうと介護される人は益々エスカレートした行動になってしまいます。
こうなると、悪循環となり決していい結果にはつながりません。
『介護する人の対応次第で軽減される』と言われると何だか責任重大だし、ならばそれなりの対応をしなければ、と思いますが現実的にはなかなか厳しいですよね。
子育てをしていた時に、我が子の寝顔を見て、カッとなって怒ってしまった自分を責めた経験はありませんか?
今度は怒らないようにしよう!って心に決めても日々のこととなると簡単にはいかなかったですよね。
頭ではわかっていても現実はそう簡単にはいきません。
ですが、それでもちょっとでも意識していくことによって、その周辺症状が緩和されるのであれば、介護する人もされる人もどちらにとってもハッピーになれるので、気負いすぎず試行錯誤しながら自分にとってベストな方法を見つけて日々を送れるといいなぁと思います。
スポンサーリンク