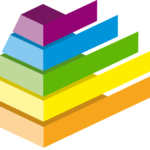こんにちは、天乃 繭です。
今回は、先日、歯周病が認知症の症状を悪化させる、という興味深い記事を読んだので紹介したいと思います。
そういえば、昔、虫歯治療の為に歯医者さんに通っていたときに、歯周病が認知症に関係している、といった内容のポスターが待合室にデカデカと貼ってあったのを思い出しました。
もちろん、その当時は、認知症なんて自分には無縁!と思っていたので、ポスターに書かれている詳しい内容などは読むこともなく、ただ大きな字で書かれたあったポスターが印象に残っているだけなのですが。。。。(今思えば、ちゃんと読んでおけばよかったなぁ~(笑))

でも、その歯周病が認知症に一体どんな影響があるんだろう?
記事の内容は、歯周病が認知症の症状を悪化させる仕組みを解明した、というものなんだけど、その記事を早速紹介してみるわね

スポンサーリンク
認知症の症状を悪化させるのが歯周病の毒素!
その記事によると、
認知症の中でも6割~7割を占めるアルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞の中にアミロイドβと呼ばれるたんぱく質の『ゴミ』が溜まって、神経細胞が段々に死滅していくことで発症する病気なんですが、その脳の『ゴミ』と呼ばれるものを増やし、認知症の症状を悪化させるのが歯周病菌の毒素である、ということがわかった、ということなんです。
実験としては、
アルツハイマー型認知症になっているマウスに歯周病菌を感染させて、そうでない健康なマウスの脳と比べてみたというのです。
わずか1ヶ月ちょっとしか経っていないのに、歯周病菌に感染したマウスでは、『ゴミ』と言われるアミロイドβの量が記憶を司る海馬で約1.4倍に増えている上に、記憶学習能力の認知機能も低下していたそうです。
この結果から、
歯周病菌に感染したマウスの脳では、歯周病菌から出される毒素や免疫細胞が細菌を攻撃するために出す様々なたんぱく質が増えていた。
そして、歯周病菌の毒素や様々なたんぱく質が増えたことによって、『ゴミ』と呼ばれるアミロイドβがたくさん作られるようになった、と考えられるそうです。
この記事、衝撃的でした。
歯周病菌に感染してわずか1ヶ月ですよ。
たったの1ヶ月でその差が明らかになるほどの数値があらわれてしまうのですよ。
これって恐ろしくないですか?!
認知症は、十数年かけて発症する病気と言われているのに、歯周病になるとわずか1ヶ月で認知症の症状が悪化していくなんて!
認知症に限ったことではないんですが、認知症そのものにスポットを充てるだけではなく、私達のごく普通の生活でのことが認知症の予防には様々に関与していることが改めてわかります。
口の中のケアをし、常にきれいに保つことで、認知症の発症や進行の抑制につなげることができるんです。
今からでも遅くはないです、今からやりましょ、口の中のケアを!
虫歯予防にも、歯周病予防にも、認知症予防にもなります!
風邪予防やインフルエンザ予防にもなるとも聞いたことがあります!
認知症になっているかどうかに関わらず、年齢にも関わらず、歯周病の予防を心がけることで、自分の為にもまわりの人達の為にもなります。
私も始めます、歯周病予防!
いつまでも心身共に健康でありたいですものね!
ここからは歯周病についてちょっと書いてみたいと思います。
歯周病ってどんな病気?
歯周病を知らない人はいないと思いますが、ここでもう一度歯周病について再確認をしたいと思います。
歯周病とは、
細菌によって引き起こされる感染症で、
- ハグキが赤く腫れたり出血したりする『歯肉炎』と
- 歯グキや歯を支える骨など歯の周りの組織が破壊される『歯肉炎』
を総称したものです。
細菌が歯と歯グキの境目に溜まっていってプラーク(歯垢)がこびりつき、『歯周ポケット』を作ってそこで増殖していきます。
歯周病の進行過程は?
(健康な状態)
歯と歯グキのすき間は、1~2mmほど
↓
プラーク(歯垢)が段々に溜まっていき、炎症が起こり始める
歯と歯グキのすき間は、2~3mmほど
↓
歯グキの炎症がひどくなり、歯周病菌が歯のまわりの組織に侵入していく
歯と歯グキのすき間は、3~5mmほど
↓
炎症が更にひどくなり、歯がグラつき始める
歯と歯グキのすき間は、4~7mmほど
↓
歯がグラグラになったり抜けたりする
歯と歯グキのすき間は、6mm以上となる
スポンサーリンク
自分でできる?歯周病のセルフチェック
下記の項目で5コ以上当てはまる場合には、歯周病の可能性があるとされています。
- 歯グキの色がピンク色ではなく、赤味を帯びていたり赤紫になっている
- 歯グキが丸く腫れぼったい感じになっている
- 疲れたりストレスを感じると歯グキが腫れる
- 歯グキが縮まって(上がって)歯と歯の間にすき間ができている
- 歯が伸びてきたように感じる
- 歯磨きをすると血が出る
- 朝起きた時、口の中がネバついている
- 歯と歯の間に物が挟まりやすい
- 最近、口臭が気になる
- 歯がしみる
- 硬いものを食べると痛みがある
- 寝ている時に歯ぎしりをする
歯周病にならないための予防と対策
歯周病菌は誰でも口の中にいる菌で、
気管に入れば『肺炎』
血液に入れば『糖尿病』『心臓病』『脳卒中』『認知症』
妊婦さんの場合には『早産』『未熟児出産』
のリスクを高めるなど様々な病気を引き起こす怖い病気です。
そんなことにならないための予防策として、
1)口の中の衛生環境を整える
- 毎日、歯と歯グキを丁寧にブラッシングして、歯周ポケットのケアをする(デンタルフロスや歯間ブラシ・液体ハミガキが効果的)
- 口の中が乾燥すると菌が増殖するので、口の中が乾燥しないためにも口呼吸を避ける
- 歯や歯グキに負担がかかるので、歯ぎしりをしないようにする
- 噛みあわせを整える
2)生活環境を整える
- 免疫力が低下すると歯周病のリスクが高まるので、疲労やストレスを溜めない
- 唾液が充分に分泌されないと細菌が増殖するので、よく噛んでゆっくりと食べる
- 睡眠をしっかりと取る
- 定期的な歯科検診を受けて、クリーニングケアをする
以上が歯周病に関する簡単な解説となりますが、いかがでしたか?
歯周病は他の病気に比べて痛み等がないので軽視しがちですが、様々な大きな病気を引き起こす原因となっています。
また、歯周病は、男性に比べて女性のほうがなりやすいとも言われています。
歯周病に限らずですが、どんな病気も単独ではなく色々な重大な病気と密接に結びついていることがよくわかると思いますので、日々の暮らしの中で自分でできることはしっかりとやって予防につなげ、いつまでも元気に過ごせるよう心掛けていきたいですね!!
スポンサーリンク