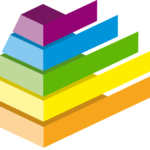こんにちは、天乃 繭です。
皆さんは、9月が『アルツハイマー月間』ということを知ってましたか?
私は、今年になって初めて知りました~。
これを書いている今はもう10月なので、『アルツハイマー月間』は終わってしまったんですが、9月の最後に開催された講演会にギリギリで参加することができました。
間に合った~!! よかった~!!
です。
スポンサーリンク
まず、この『アルツハイマー月間』についてですが。。。
世界アルツハイマーデー(9月21日)は、国際アルツハイマー病協会が、認知症への理解をすすめ、認知症本人やその家族への施策の充実を目的に1994年に制定。
また、9月を世界アルツハイマー月間として世界各国で啓発活動を行っています。
とあります。
そして、『アルツハイマーデー』である9月21日を中心に、全国各地でお城やタワー、企業のビル、病院や市役所などが『認知症支援の象徴』を表す『オレンジ色』にライトアップされたり、ポスターやリーフレットを作成して配布するなど、様々な活動を行っているんだそうです。
それ程大規模なものだったんですね~
日本だけでなく、世界各地で共通して行われています。
関心がない、ということは恐ろしいですね!
母が認知症になるまで、私は『認知症』には全く無関心でした。
そして母が『認知症』になってからもこの『アルツハイマー月間』のことは全く知らずにいました。
もう25年も前から世界各地で9月になると様々な活動が行われていたというのに。
お恥ずかしい限りです。。。。
でも、それにしても、お城やタワーなどがオレンジ色にライトアップされているのなんて、一度も見たことがありません!
誰からも聞いたこともありません!
自分の無関心さを棚に、それも単なる棚ではなく、大棚にあげて言わせてもらっちゃいます。
これだけ『超高齢化』や『認知症』が社会の大きな関心事になっているのに、そして25年も前から活動をしているのに、認知度というか人々への浸透度があまりにも低すぎませんか~?!
もっとニュースやマスコミなどで取り上げて紹介し、少しでも多くの人に知ってもらえばいいのにと思います。
不満はそのぐらいにしておいて、そろそろ参加した講演会についてお伝えしたいと思います。
この『第25回世界アルツハイマーデー記念講演会』の講師は、東京慈恵会医科大学附属病院 メモリークリニックの繁田雅弘先生でした。
知っていらっしゃる方、いますかぁ?!
私はこの講演を聴きに行く前に、たまたま認知症の特集を掲載していた雑誌『クロワッサン』を読んで繁田先生のことを知ったのです。
繁田先生の認知症に対する考え方、捉え方にとても共感がもて、この講演会の講師が繁田先生であること知ってぜひ聴きに行ってみたいと思っていたのです。
世間一般でよく言われている認知症、医学的な立場からみる認知症は、『段々と〇〇ができなくなっていきます』『○○が段々にわからなくなっていきます』といった、マイナス面に焦点を当て、『認知症になったらおしまいだ』『認知症になったら何もわからなくなる』など、悲観的・絶望的に思われていますが、繁田先生は違うんです。
雑誌『クロワッサン』の中でも、講演の中でも言ってました。
『認知症』は決して特別な病気ではなく、誰でもがなり得る可能性のある身近な病気だと。
だから、〇〇ができなくなっていく、○○がわからなくなっていく、といったマイナス面に目を向けるのでなはなく、『今できる』ことに目を向け、その『できる』力を出来る限り持続していく、そしてそのことによって生きる喜びや自信、心の安定につなげていくべきだ、との考えをされています。
また、『認知症』とは、誰もが避けることのできない『老化』の延長線上にあるもので、人生100年時代といわれる現代では、その症状の現れが人によって早いかちょっと遅いかだけの違いにすぎないとも言ってました。
スポンサーリンク
更には、繁田先生が強調して言っていたことがあります。
それは。。。
『認知症予防』とは、『認知症』にならないための予防ではない
と。
新聞や雑誌、テレビなどで、『認知症予防』のために、計算ドリルや漢字ドリルをやって脳を活性化させるといい、と言っているのをよく聞きますよね。
でも、計算ドリルや漢字ドリルをやっても『認知症』の予防にはならないんだそうです。
えぇ~、そうなのぉ?
ですよね。
あんなにテレビなどで言っているのに!!
『認知症』になること自体は予防できないんだそうです。
『認知症予防』の正しい意味とは、『認知症』にならない予防ではなく、『認知症』になったときに『症状の進行を緩やかにする予防』という意味だそうです。
人は『歳を取りたくない』と思ってもそれを予防することができないのと同じで、『認知症』になること自体を予防することはできないとのことでした。
なので、計算ドリルや漢字ドリルをやることが好きな人はいいんですが、好きでもないのにただ予防のためにと思ってやっていても、かえってストレスになるだけで効果はないと繁田先生は言ってました。
それよりも、『認知症』になる前から、例え『認知症』になっても好きで続けていける何かを見つけて(=趣味をもつ)、それを今からやっているのがいいそうです。
例え『認知症』になっても、そういう楽しみがあることが生きる張り合いになり、進行を遅らせることにもつながっていくのだそうです。
そして、研究結果から、この10年~20年の間に、アルツハイマー型認知症の進行はとても緩やかになって、その進行は半分~3分の1になったそうです。
軽度の認知症の期間は2倍~3倍に長くなり、軽度のまま人生を全うする人も増えてきた、と言ってました。
誰でもがなる可能性をもっている『認知症』。
認知症の診断テストを開発した長谷川先生も『認知症』であると公表されてましたよね。
長年、学校の先生をしていた人、企業のトップだった人。。。
まわりを見れば、『え、この人が?』 と思うような人までも『認知症』になっている世の中です。
繁田先生が言っていた、
『誰でもが認知症になる可能性がある』
『認知症は予防できない』
まさしくその通りだと思います。
だからこそ、今『認知症』とは無縁である人達も、現在進行形で認知症の介護をしている人も、こういった講演などを通じて『認知症』について少しでも理解を深め、誰でもが安心して過ごせる社会になっていくことが何より望ましいのではないかとつくずく感じました。
最後にちょっと余談ですが、
上記でも書いたように『認知症支援の象徴』を表す色は世界共通で『オレンジ色』なんですが、京都府宇治市では『オレンジ色』ではなく、『レモン色』にしているそうです。
朝日新聞に出てました。
新聞に掲載の宇治市担当職員によると、
レモンをオレンジより薄い色、ととらえてのネーミング。 オレンジ = 認知症として暮らしが大変になる前に、早期のレモンの段階からつながりを持ち、支援をする意思表示。
と説明しています。
何となく心がホッとして軽くなるのを感じませんか?
『オレンジ色』になる前の『レモン色』。
ん~、いいアイデアです! (← ちょっと偉そうに言ってみました!!)
私の個人的な意見ですが、私も『オレンジ色』よりも『レモン色』のほうがいいです。
『オレンジ』より柔らかな印象を与えるし、深刻な気分にならなくていいですよね。
みなさんはどんな印象を持ちますか?
スポンサーリンク