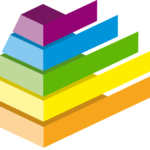こんにちは、天乃 繭です。
みなさんは『誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)』って知ってますか?
よく耳にする言葉ですよね。
よく耳にはしますが、私は言葉を知っているだけで詳しくは知りませんでした。
認知症の母との生活を通して色々な本を読んだり調べたりするうちに、少しずつですが色々なことの知識が身に付いてくることはありがたいことですよね。
どんなこともそうですが、『知らない』ということは本当に恐ろしいことだと最近つくづく思っています。
スポンサーリンク
前回の『認知症の人のうたた寝。ただ眠いだけ、と思っていませんか?それ、傾眠かも?!』でも書きましたが、その『傾眠』と同じく『いつまでも口の中に食べ物が入っていてなかなか飲み込めない』という母の今の状態がとても気になっています。
毎晩、夕食を食べ終わるのにすごく時間がかかり、ひどい時には2時間ぐらいかかってしまう時もあるんです(レストランのフルコース並みですよね(笑))。
そして、食べるのにかかる時間には関係なく、食べ始めてから少し経つとウトウトとしだし、半分寝ながら食べるようになるんです。
しばらくすると、まだ食べ終わってもいないのに横になってしまいます。
ご飯を食べている最中に眠くなったから横になったというのならまだいいのですが、横になりながら口だけはいつまでもモグモグさせていて一向に飲み込む気配はないんです。
ほとんど寝ている状態なので、ノドに詰まったり気管に入ったりしたらそれこそ大変です。
起き上がって口の中の物をちゃんと飲み込んでから横になるか、口の中に入っているものを出すかして!
と言うのですが、こういう時には返事もせず無視状態。
危ないから言っているのに、ホントに頭にきちゃいます!!
こんな時はつい怒り口調になってしまいますね。
母もしぶしぶ上体を起こして口の中の物をペッて出すんですが、出したはずなのにまた口をモグモグモグさせていて。
さっき出したんじゃなかったのぉ?! です。
『なかなか飲み込めない』ことと同じく『口の中の物を吐き出す』こともできにくくなっているんですかね?!
もしくは、飲み込んだと思っているものが本人も気付かないままノドの近辺に残っていて、それがまた口の中に戻ってきているのかもしれないですね。
母に聞いても、はっきりした確かなことがわからないのが何とも歯がゆいです。
そんなことをきっかけに、高齢者や認知症の人の『なかなか飲み込めない』ということに関して本を読んだり調べたりしていく中で、今回のテーマの『誤嚥性肺炎』について知るきっかけとなったのです。
高齢者の場合には、主だった症状が出ていなくても『誤嚥性肺炎』を起こしている可能性もあるので、周りの家族が充分注意して異変に気付き、早期に発見することが重要と書かれてありました。
そうだんたんですね。
私はてっきりいわゆる普通の肺炎のように、症状としては本人も周りの人もすぐに気付くものだと思い込んでいました。
目次
高齢者の誤嚥性肺炎とは
高齢者の場合、飲み込む力(= 嚥下 えんげ)が衰えてきているので、食べ物やツバなどを飲み込むときに誤って気管に入ってしまうことがあります(= 誤嚥 ごえん)。
それが吐き出されずに、気道を通って細菌が肺の中まで入り込み、炎症を起こしてしまうのが『誤嚥性肺炎』です。
高齢者の肺炎の約70%がこの『誤嚥性肺炎』で、気管に入ってしまったことを本人も気付かないうちに繰り返して悪化していくそうです。
また、『誤嚥性肺炎』は一度かかると再発しやすく発症の度に重症化する上に、耐性菌ができて治りにくくなる病気なんです。
何とも恐ろしいですね!
高齢者の誤嚥性肺炎の原因は?
1)誤って食べ物やツバが気管に入り、細菌が繁殖して炎症を起こす。
高齢者の場合には、口の中に食べ物が残っていると、気付かないうちにツバと一緒に少しずつ気管に入っていくこともあります。
⇒ これ、まさしく母が気を付けなければならないことだと思いました。
私達は気管に入ってしまった時には咳込んだりすることでそれを外に出すことできますが、高齢者の場合には少しずつ気管に入ってしまうので本人も周りもなかなか気付けないですものね。
最初のところで書いたように、口の中の物を吐き出したにもかかわらず、すぐまた口をモゴモゴさせているのはやっぱり飲み込めなかった食べ物がノドの辺りに残っていたんだと思いました。
2)胃液と一緒に胃の中の物が食道を逆流し、胃酸や消化液などによって気道の粘膜が損傷することによって誤嚥性肺炎を起こす。
高齢者の誤嚥性肺炎の症状は?
一般的には
- 37.5度以上の熱が出る
- せきが出る
- たんが出る
- 息苦しくなる
などの症状が典型的な症状です。
ところが高齢者の場合には、上記のような典型的な症状が出にくく、気付いたときにはかなり進行してしまっていることもあるので、いつもと違う様子に周りの人達がいち早く気付いて対応することが重要とのことです。
では、高齢者のどんな症状に気を付けたらいいのでしょうか?!
次のような症状が出ていたら要注意です。
- 身体のだるさや疲労感が常にある
- 呼吸数が増えている
- 食事に時間がかかる
- 食べる量が減り、体重も減った
- 水分をあまり摂りたがらない
- 声がかすれる
- 寝ている時に急に咳込む
- 食べ物がなかなか飲み込めない
- よくムセる
- 食べ物が口の中に残っている
- オシッコの量が減った
- 食後にタンが増える
- 原因不明の傾眠がある
- ノドがゴロゴロゼイゼイしている
などです。
⇒ 母は、呼吸数・声がれ・食後のタン・ノドがゴロゴロゼイゼイしている の4つ以外は全て当てはまってしまっています。
今回『食べ物がなかなか飲み込めない』という状態について調べていて知った『誤嚥性肺炎』ですが、まさにこの『誤嚥性肺炎』の症状だったので、ビックリでした。
スポンサーリンク
高齢者の誤嚥性肺炎の検査方法は?
誤嚥性肺炎の検査方法としては
- 血液検査
- レントゲン又は胸部CT
- 問診
などです。
高齢者の誤嚥性肺炎の治療方法は?
誤嚥性肺炎の治療方法としては
肺の炎症を起こしている細菌を抗菌剤によって死滅させる
高齢者の誤嚥性肺炎の予防方法は?
誤嚥性肺炎の予防方法としては
- 規則正しい生活や栄養のバランスのとれた食事を摂って免疫力を高める
- 飲み込む力を鍛える
- 口の中を清潔に保ち、細菌を減らす
- 食事をする時の姿勢に気を付ける
- 食後しばらくは横にならない
などです。
ノドは40代から衰え始めるそうです。
食事中にムセることが多くなったり、薬が飲みにくくなったり、ツバを飲み込む時に気管に入りやすくなったりするのは、衰えのサイン。
避けては通れない「老化」ですが、上記に挙げた5つは決して難しいことではないですよね。
衰えを感じる前から少しずつでも日々取り組むことで、高齢になった時の予防につなげていきましょう!!
ノドを鍛えて飲み込む力をつける方法として、アゴの下に両手の親指の腹の部分を当て、アゴは引く感じに、親指は押さえつける感じにするといい、と以前本で読んだことがあります。
効果のほどはわかりませんが、簡単にできることなのでスキマ時間でやってみようかと思っています。
また、65歳以上から自治体の助成で接種可能な『肺炎球菌ワクチン』を皆さんは知ってますか?
誤嚥性肺炎の原因となる菌は、この肺炎球菌感染症の一つと言われているので、肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けることで『誤嚥性肺炎』の予防にもつながるそうです。
ただ、この『肺炎球菌ワクチン』は65歳から5年おきに受けられるのですが、自治体の助成で受けられるのは1人につき1回のみになります(過去に接種したことがない人が対象)。
またこのワクチンは2種類ありますが、自治体の助成によって受けられるのは1種類(ニューモバックスと呼ばれるもの)のみとなります。
この肺炎球菌ワクチンに関する詳しいことは、各市区町村に問い合わせしてみてくださいね。
母は80歳の時に自治体から接種のお知らせが来ていたのですが、この頃は知識もまだなく、受けようと思ったときには有効期間を過ぎてしまっていて受けることができませんでした。
次に公費で受けようとすると85歳になってしまいます。
85歳というとまだ先のことになってしまうので、自費になってしまいますが、かかりつけ医に相談して、必要なら今年受けようかと思っています。
最後に
高齢者の『誤嚥性肺炎』は、本人も周りも気付かないうちに進行していることが多く、症状としても典型的な症状が出るとは限らないことがわかりました。
私の母の場合は、熱が出ていることがないので大丈夫かと思いますが、その他の症状としてはかなり当てはまってしまいました。
とにかく、すぐ寝てしまうこと、寝ながら口の中には食べ物がいつまでも入っていること、吐き出したはずなのにまた口の中に食べ物が入っていること、飲み込む力が弱っていることなどが気になるところです。
誤嚥性肺炎を引き起こさないよう、気を付けて見ていこうと思っています。
また、今度病院を受診した時には『傾眠』と『誤嚥性肺炎』について担当医に聞いてみたいと思っています。
その結果については、後日また書かせてもらいますね。
スポンサーリンク