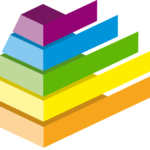こんにちは、天乃 繭です。
2018年7月16日付けの朝日新聞に、『一口に認知症と言っても、【困りごと】はそれぞれ違う』という記事が載ってました。
この記事によると、その人は、51歳の時に認知症と診断されたのですが。。。
私の場合、前日の出来事や人の顔なんかは割と覚えています。
認知症=もの忘れ、じゃないんですよ。
ただ約束は覚えていても、時計の数字が読み取れない。
文字もいまは自分の名前も書けません。
家を出るときも玄関の鍵穴にキーがうまく入らず、時間がかかってしまうんです。
とありました。
今一番の困りごとは、なかなか服の袖に手を通せないことだそうです。
スポンサーリンク
この新聞記事の内容は。。。
51歳の時に認知症と診断され、周囲に知られたくなくて家にこもっていたけれど、人間ドッグの受診をきっかけに思い切って自分が『認知症』でることを周囲に伝えたら、その後どのような場面でも周りの人が色々とサポートしてくれたり助けてもらえるようになった。
『認知症だと伝えたらこんなに楽になるんだ』ということを知って、自分らしさや笑顔を取り戻すことができたので、それを伝えようと講演を始めた、というものです。
そしてその記事の最後には、
何でも一人でこなしてきた母親が、計算もできず、漢字も書けない。長女は最初そんな現実を受け入れられず、会話もできない苦しい時期もありました。
と。
そして更には、
尊敬できる母親です。
診断後は家にこもって泣いていた母が、少しずつ立ち直り、難しい病気に負けずに闘っている。人前で堂々と話す姿は想像もできなかったけれど、誇らしいと思う。
と息子さんの感想で締めくくっていました。
娘さんの思い、すっごくわかります。
私もそうでした。
母が認知症になった現実をなかなか受け入れられなかったです。
息子さんの感想は、すごいな~!! って思いました。
私もいつか、心から母を『誇らしい』と思えるようになりたい、そうなろう! と思います。
そんな風に思いながら記事を読むと共に、私は、『やっぱりそうだよね!』という思いも改めて持ったんです。
この新聞記事は、自分が『認知症』であることを隠すことなく周囲に伝えることで、手助けしてもらう機会が増えたり自分らしさや笑顔を取り戻すことができるようになった、ということを伝える記事だったのですが、もちろんそれは素晴らしいことだし、大切なことだと思います。
けれど、今回私がそれだけではなく、『やっぱりそうだよね!』と思ったことと言うのは。。。
冒頭にある言葉、
『一口に認知症と言っても、【困りごと】はそれぞれ違う』
ということなんです。
スポンサーリンク
『認知症』の代名詞みたいに言われている『もの忘れ』ですが、確かに多くの『認知症』の人に見られる代表的な症状であることは確かですが、私達は『認知症=もの忘れ』という固定観念を持ってはいないでしょうか?
確かに『認知症』に現れる事象には多くの共通点があると思いますが、決してそれだけで決めつけられるものではないですよね。
例えば、『認知症』の周辺症状の1つでもあり、私の母にも見られた症状で、夕方になると『帰る!』と言い出す『帰宅願望』。
夕方になると『ウチに帰る!』と言い出す症状は誰でも同じなのかもしれません。
けれど、その『帰る!』と言う背景は人それぞれ違うはずです。
以前住んでいた家が懐かしかったり心配に思ったりする気持ちから『帰る!』と言う人。
今いる家に居場所が感じられないから『帰る!』と言う人。
娘時代の実家がよかったと思っているから『帰る!』と言う人。
などなど、同じ『帰る!』でもその言葉を発する元になる思いは様々なはずです。
その元が何であるかは、当然のことですが本人しかわからないのです。
そしてその元が様々であるならば、私達介護をする人の対応もそれに合ったものでなければなりませんよね。
このことは『帰る!』という症状に対してだけではなく、全てに言えることだと思うのです。
だからこそ、私は極力『認知症』の人の真の声を聞いて知ることが介護をしていく中でとても大切なことなんじゃないかと思うのです。
『認知症』の人が何を思いどう感じているのか。
これを知ることで私達が学ぶものはたくさんあると思うし、そこからしか学べないとも言えると思うのです。
私達介護をする人は、『認知症』の人の真の思いを聞けなければ、ただ『想像する』だけしかできないですよね。
私の母は、自分が『認知症』であるということを自覚しているのかどうかはわからないです。
本人が『認知症かも』と思っている時期には、私達家族も本人と同じように混乱している時期でもあるので、『今どんな思いをしているか』なんて聞ける余裕はないですよね。
医者から『認知症』と診断された時には、不安な思いや混乱など当時感じていた思いを聞くことは、大抵の場合にはもうできなくなってしまっているんじゃないでしょうか?
母からその当時のことを聞くことはもうできません。
だからこそ、私はこれから先、『認知症の人の生の声、本心』を聞く機会をできるだけ増やし、母との生活に活かしていこうと思ってます。
『認知症』ということに対して、単なる『想像』や『固定観念』だけで対応するのではなく、『認知症の人の生の声や本心』を聞き、知ることによって学んでいく。
そうすることによって、私達家族はもっともっと寄り添って歩んでいけるのではないかと思っています。
日常生活を送っていれば、今までと同じくイラつくことも多々起こるでしょう、ケンカをしてしまうこともあるでしょう。
でも、『認知症』の人による『生の声や本心』を聞いて人それぞれであることを知ることによって、母が当時何を思い感じていたのかを想像し、母のバックグラウンドと合わせながら母の心に少しでも近づいて、これから先、母と向き合っていけたなら、母も私ももっともっと楽しく暮らせるのかな~、なんて思っています。
スポンサーリンク