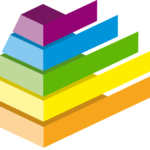こんにちは、天乃 繭です。
みなさんは、『難聴』が『認知症』にかかる可能性を高める要因の1つ ということをご存知でしたか?
2018年8月1日付けの朝日新聞に、『難聴』と『認知症』との関連についての記事が載っていたので、もう既に読まれた方もいらっしゃるかと思いますが、ここに紹介させてもらいますね。
タイトルは、『認知症予防 「誰でもなる」前提に』
サブタイトルは、『要因の一つ 難聴は補聴器で対策』と『発症の先送りめざす』
です。
『認知症』と『難聴』?!
この2つが一体どんな関係があるんだろう?! と興味津々で読んでみました。
スポンサーリンク
その中の記事を一部抜粋してみると。。。
認知症にかかる可能性を高める要因はいろいろ指摘されている。
最近注目されているのが聴力が低下する難聴だ。
認知症を招く要因の1割弱を占めるともいわれている。
難聴の人にとって補聴器は頼れる存在だが、つけただけでうまく聞こえるとは限らない。
聞こえない状態に脳が慣れ、補聴器を通じた音をうるさく感じやすいのだという。
リハビリに参加していた女性は「前は周囲の会話が聞き取れず、『聞こえるふり』をして笑うだけだった。いまは話の中身に入れて楽しい」。
認知症のリスク要因として難聴が大きく注目されたきっかけは、英医学誌が昨年発表した報告書だ。
これまでの研究をもとに「(高齢者を含む)中年期以降の難聴は、認知症の要因の9%を占める」とされた。
難聴の人はそうでない人に比べ、認知症のリスクが1.9倍あるという。
難聴がリスクを高める理由はまだはっきりとはしていない。
聴覚からの刺激が減って神経の活動が落ちるといった直接的な作用や、聞こえないことで社会から孤立しがちになるなどの間接的な影響が考えられている。
いま認知症の治験に使われる薬は、症状の進行を抑えるだけで効かないことも多い。
予防への期待は高まるが、「これをすれば確実に防げる」といった方法はない。
厚生労働省研究班の調査によると、認知症にかかる人の割合は65~69歳では約3%だが、85~89歳では41%、95歳以上では80%に達する。
認知症介護研究・研修東京センターのセンター長は「長生きをすれば、認知症になるのを避けるのは実際には難しい」と指摘する。
自分もいつかは認知症になることを踏まえたうえで、その先送りをめざすのが予防だととらえる。
運動をし、喫煙や生活習慣病を避けることは、がんや脳卒中、心身の活力が落ちるフレイルなどを防ぐことにもつながり、生活の質を上げる。
認知症を防げなかったとしても取り組む意味はある。
と書かれていました。
つまり、
認知症を治す方法が確立していない中、予防への関心が高まっているけれど、その確実な手段はない。
「いつかは誰でも認知症にかかる」ということを前提に、認知症のリスクとなる要因を避けることで、認知症の発症の先送りを目指そう、という内容です。
私の知識不足によるものなのかもしれませんが、私は『認知症』と『難聴』が関係があるんなて、全然知らなかったです。
なので、この記事、私はとても興味深く読んだのですが、その中でも特に興味を引いたことが2つありました。
それは。。。
1)補聴器をつけてのリハビリに取り組んでいる女性の言葉の、『前は周囲の会話が聞き取れず「聞こえるふり」をして笑うだけだった。』
2)聞こえない状態に脳が慣れ、補聴器を通じた音をうるさく感じやすい
の2つです。
スポンサーリンク
この2つは、私の母にも共通することだったのです。
私の母は若い頃から極度の近視の上に重度の乱視もあって、メガネをかけてはいますが、ほとんど視力が出ていない状態で現在に至ってます。
なので、旅行に行った時など、遠くの景色や珍しいものなどを発見すると母にも見せてあげようとするのですが、目の悪い母にはなかなか見つけることができず。。。
何度も『あそこ、あそこ』と指を指しながら教えてあげると、ようやく『あ、見えた、見えた、あれね!!』となっていました。
当時は、母の『見えた』『わかった』の言葉をそのまま信じて過ごしていましたが、何年か経ったある時、母が『見つける努力はしていたけど、どうしてもわからない・見えないことが続くと段々見ることが面倒になって、見えたふりをしていたのよ』と。
ある時から、ず~とそうしてきていたらしいのです。
見えてもいないのに、『あ~、あれね!!』と。
その言葉にすっかり騙されていたわけですが(笑)、母のその気持ちもわかるような気がします(泣)。
見えない・わからない、という自分への苛立たしさと周りの人に対する気遣いとからだったんでしょうね。
上記の新聞記事の女性と同じです、『耳』か『目』かの違いだけで。
この『ふり』は気を付けないといけないですね。
母の場合も、見えた『ふり』を重ねていくうちに見えない状態に脳が慣れてしまったんですね、きっと。
『ふり』を続けていると脳が聴こえないこと、見えないことなどが当たり前の状態となって、外からの情報を受け取らなくなってしまうのですね。
脳の神経細胞が活性されないから、段々と『認知症』につながっていってしまうのです。
私は、『見ること』『聴くこと』だけではなく、『五感』が『認知症』と深いつながりを持っていることを改めて実感しました。
『見ること』『聴くこと』『味わうこと』『嗅ぐこと』『触れること』。
この『五感』は脳にとってとても重要なんだと思います。
ただただ惰性的に感じているだけではダメなんですね。
見ることで、聴くことで、味わうことで、嗅ぐことで、触れることで、脳が刺激されるんです。
一つ一つの『感覚』に意識を傾けてそれを感じ取ることによって脳の神経細胞が活性され、そのことが『認知症』の予防につながっていくのではないでしょうか。
日々の忙しさの中で、一つ一つに意識を傾けて感じてなんていられない、なんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ほんの少しのことでも構わないと思うのです。
日々の小さな小さな積み重ねが、何十年か先の自分を創っているんだと思えば、ほんのちょっとの時間を使うことぐらい何でもないですよね。
『認知症』の初期段階は『もの忘れ』ということは誰でもが知っていることですが、実際は『もの忘れ』よりも先に『匂いがわからなくなる』のだそうです。
そしてこの『嗅覚』は訓練すれば、低下した機能を蘇らせることもできるそうです。
その方法はいたって簡単。
果物や野菜、料理、アロマ、などなど何でもいいのです、とにかく匂いを嗅ぎ、そのものを感じることだそうです。
たったそれだけのことで『嗅覚』の機能が活性化され脳も刺激されるのです。
今回の新聞記事、そして母の言葉から、この嗅覚に関することも合点がいきました。
五感を働かせること!
そうすることによって脳を刺激して活性化させ、将来誰でもがかかるかもしれないと言われている『認知症』を予防していきたいと思っています。
スポンサーリンク