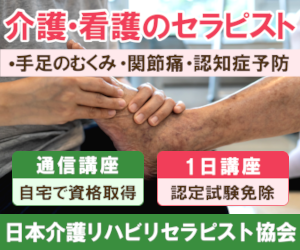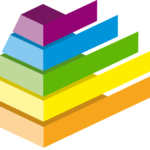こんにちは、 天乃 繭です。
要介護・要支援認定の申請によって、要介護度や要支援度が確定しますが、その認定の有効期間は通常は1年間となります。
この一年の有効期間内に心身の状態が大きく変化した場合などには、『区分変更申請』という申請を行うことが可能なんですが、特に問題がなければ一年間はこの認定のままで介護保険サービスを受けていきます。
(区分変更申請については、『要介護認定を受けたけど、やり直しはできる?区分変更申請で再認定を!』で詳しく書いてありますのでそちらを参考にしてみてくだいね)
そして、一年後も引き続き介護保険サービスを利用していくために、有効期間の満了する2か月前に各市区町村から『要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ』及び『介護保険 認定更新申請書』が送られてくるので、有効期間内に更新の手続きをしなければなりません。
有効期間が切れるまでにまだ2ヶ月もあるから、と思っていてはダメですよ~
あっという間に2ヶ月なんて経っちゃいますからね~
更新申請書を記入して提出 ⇒ 調査員が自宅を訪問しての調査 ⇒ かかりつけ医が意見書を書く(← これは各市区町村がかかりつけ医に書類を送ってくれるので、私達が何かやることはありません) ⇒ 審査 ⇒ 新しい要介護度の決定
となるので、意外と時間がかかってしまいます。
なので、のんびりはしていられません。
有効期間内に手続きが終わらないと、経過してしまった分は全額負担となっては大変です。
そうならないためにも、早め早めの手続きをしましょう!!


スポンサーリンク
要介護更新認定の申請方法
わからないことだらけでスタートした最初の要介護認定・要支援認定の申請でしたが、あっという間に一年が過ぎて行く感じですよね。
ようやく介護保険サービスを利用した生活にも慣れてきたかと思った丁度その頃、今度は要介護・要支援の更新の手続きが必要となってくるのです。
休むヒマがない感じですよね、次から次へと手続きばかりで!!
上記でも書きましたが、要介護・要支援認定の有効期間は通常1年となります。
なので、認定の有効期間満了日の2か月前から認定の更新手続きができるようになるので、この間にまた更新の手続きをしなければなりません。
さて、その更新申請方法ですが、また難しくって面倒なんじゃないの? って思っている人も多いかもしれません。
でも、安心してくださいね、難しい新たなことはありませんので。
最初に申請したことと同じことを繰り返すだけです。
もう経験済みですものね、大丈夫です。
では、もう一度更新申請をするにあたっての流れをみていきましょう。
更新申請のお知らせが各市区町村より届く(認定有効期間満了の約2か月前頃)
↓
要介護更新認定・要支援更新認定申請書 記入&提出
↓
調査員による調査
↓
要介護認定
↓
結果の通知
となります。
最初の認定申請との違いは?
更新申請の流れとしては、初めて認定の申請をした時とほとんど同じなのですが、違う点を挙げるとすれば、
- 更新認定の申請書が、認定期間有効満了日の約2か月前頃、各市区町村から郵送されてくる
- 更新認定申請書は、担当ケアマネージャーによる代行提出も可(もちろん自分でも手続きしてもOK)
- 調査員は、各市区町村の担当職員ではなく、地域包括支援センターに属している調査員が調査に来る
- 調査日当日、担当ケアマネージャーも同席してくれる(日程の都合上、同席しないこともあり)
の4つです。
更新申請書は、初めて申請した時の用紙を見てもらうとわかると思いますが、初めての申請と更新申請とを兼ねた申請書となっているので、新規で申請したものとほとんど同じです。
なので、『要介護認定の申請方法』で説明している通りに記載すればOKなんですが、下記にもその記入方法を書いておきますね。
また、初回と同じように、主治医にも『意見書』が各市区町村より郵送されますので、その時期が近づいてきたら受診時に主治医にその旨を伝えておくといいと思います。
①被保険者(本人)
<個人番号>
マイナンバー12ケタを記入します。
<被保険者番号>
介護保険被保険者証の『0000』から始まる全10ケタの数字なんですが、『更新申請』では既に印字されています。
間違いがないかどうかの確認のみとなります。
<申請年月日>
更新申請書を記入した日、もしくは各市区町村の介護保険課に提出する日を記入します。
<氏名・生年月日・性別>
要介護更新認定を受ける本人の氏名と生年月日・性別を記入するのですが、既に印字されています。
<電話番号>
要介護更新認定を受ける本人の電話番号を記入します。
<前回の要介護認定の結果等>
この1年間で認定されていた要支援・要介護度の数字に〇をつけます。
また、その区分での有効期間を記入します。
わからない場合には、
・介護保険被保険者証に2ページ目
・郵送されてきた更新申請書類に同封されている『要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ』
に書かれてあるので、見てみてくださいね。
その下の欄は、14日以内に他の自治体から転入した人に対してのものなので、該当する場合には記入してください。
②申請者等
<氏名>
本人以外の家族が申請する場合に、その人の氏名を記入します。(押印は不要)
<本人との続柄>
本人以外の家族が申請する場合に、本人との続柄を記入します。
<住所と電話番号>
本人以外の家族が申請する場合に、その人の住所と電話番号を記入します。
<提出代行者欄>
次に挙げる5種類に属する人が申請を代行するときに、名称と氏名(押印)・住所・電話番号を記入します。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
③本人の居場所
- 1 住所地
- 2 病院・施設
- 3 その他(家族宅)
の中から必ずどれか選び、〇をつけます。
本人の居場所が、『1の住所地』以外の場合には、下記の項目を記入します。
- 病院名・施設名・家族名
- 住所と電話番号
- 予定期間
④主治医
この欄は、主治医に書いてもらうのではなく、申請者が記入します。
ここに記載した主治医に、各市区町村が『意見書』というものを郵送し、本人がどのような状態であるか等を主治医が書いたあと、また各市区町村へ返送をしてくれます。
もし複数の医療機関を受診していたとしても、その中から1人の先生のみを選んで記入します。
この『意見書』に関しては、私達は一切何もすることはなく、各市区町村と主治医とでやり取りするので、主治医となっている医療機関名や住所、主治医の名前等を書くのみで大丈夫です。
⑤2号被保険者(40歳~64歳)
この欄は、該当する方のみ記入してください。
その際は、必ず医療保険証の写しも添付してくださいね。
⑥介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために ~ 提示することに同意します。
この欄は、ケアマネージャーがケアプラン作成のために、調査票や主治医の意見書を開示してほしいと要望した時に、開示しても差し支えなければ署名をします。
*この欄に署名をしたからといって調査票や主治医の意見書にどのようなことが書かれたあったのか、その内容についてケアマネージャーに聞くことはできないのですが、1年後の要介護認定更新のときに思ったような結果が得られず、再度認定のやり直しの手続きが必要となったときにはとても有効となりますので、署名をすることをお勧めします。
表面は以上となりますが、裏面もありますので引き続き裏面の書き方を簡単に説明しいきますね。
①申請理由
この欄は、複数回答可なので、該当するものに〇をつければいいのですが、更新申請の時には
2 更新のため
に〇をつければいいと思います。
②ご本人の状況(差し支えない範囲で構いません。)
『診断名』の欄
『アルツハイマー型認知症』とか『レビー小体型認知症』などの診断名を書きます。
『身体面、認知面の状況』欄
親の日常生活での様子や身体面について、極力詳しく書くことをお勧めします。
私の経験上、こんなことはささいなことだから書かなくてもいいかな、なんて思わず、できるだけ色々なことを書いたほうがいいと思います。
この欄で書き切れないときや本人を目の前にして言いにくいことなどは別の紙に書いて、この更新申請用紙に添付してもいいと思います。
昨年初めての更新申請の時、口頭でのみ伝えていましたが、思うような介護度にならなかったこともあり、今年の更新申請からは紙に書いて調査員の人に渡すつもりでいます。
絶対にそのほうがいいと思いますよ!!
私が思うに、この欄に記入したこと、別紙を利用して書いて渡したものは要介護認定の決定にかなり重要な項目になっていると思います。
もちろん後日調査員が来て実際に親の様子等をチェックするのですが、その時に口頭で伝え切れない事もあるし、例え伝えたとしても調査員の人が忘れてしまうことも考えられます。
そうなっては、要介護認定に大きく影響してきますので、しっかりと書いて現状を正しく伝えたいですね!
③認定調査時の同席者について
調査員による調査が行われる時に、同席できる家族がいるかどうかについて、必ずどちらかを選択する必要があります。
この調査のときには、日常の親の様子を知っている家族が極力同席するようにしましょう。
そして、この欄に記載した連絡先に、後日調査員から電話連絡があり、調査日を決定します。
④その他の連絡先
ここは、本人や申請者に連絡がつかなっかた時に使用するものです。
もし該当する人がいなければ記入する必要はありません。
私は、無記入のままにしています。
⑤調査員に事前に知らせておきたいこと
この欄では、ここに記載されている通り、予定している外出や調査時に配慮してほしいことなどがあれば記入します。
私の母の場合には、週5でデイサービスに通っているということの他に、本人は自分が認知症であるとの認識がないので配慮してほしい旨を書きました。
どんな細かいことでもいいと思うのです。
伝えておいたほうがいいと思われることは、どんどん書いておきましょう!
更新申請書の書き方については以上となります。
認定期間満了日までの2か月の間に、上記のような更新申請書の受理~結果の通知までが行わなければならないので、ちょっと慌ただしいです。
新規の申請の人が優先となることもあったり、また、更新申請をする時期に、新規の人や更新の人が多いと結果が出るまでに時間がかかってしまいますので、担当ケアマネージャーと相談しながら早め早めの手続きをお勧めします。
スポンサーリンク
まとめ
最初に要介護認定を受けてからの有効期間は通常1年間です。
引き続き要介護サービスを受けるには、有効期間満了日の約2か月前~満了日までの間に更新手続きをしなければなりません。
その更新手続きは、初回の認定手続きとほぼ同じなので難しいことはないかと思います。
上記の更新申請の書き方を参考に、早めに記入・提出することをお勧めします。
更新申請~結果通知までの流れは、
更新申請のお知らせが各市区町村より届く(認定有効期間満了の約2か月前頃)
↓
要介護更新認定・要支援更新認定申請書 記入&提出
↓
調査員による調査
↓
要介護認定
↓
結果の通知
となっています。
新規申請手続きと更新手続きとで違う点としては、
- 更新認定の申請書が、認定期間有効満了日の約2か月前頃、各市区町村から郵送されてくる
- 更新認定申請書は、担当ケアマネージャーによる代行提出も可(もちろん自分でも手続きしてもOK)
- 調査員は、各市区町村の担当職員ではなく、地域包括支援センターに属している調査員が調査に来る
- 調査日当日、担当ケアマネージャーも同席してくれる(日程の都合上、同席しないこともあり)
の4つです。
主治医による『意見書』が更新手続きの時にも必要となります。
最初の認定有効期間満了の約2か月ぐらい前に受診した時に主治医に、更新認定のため各市区町村から『意見書』が届く旨伝えておくといいですね。
また、更新申請時の調査員による調査では、担当ケアマネージャーも日程を合せて同席してくれることもあります。
一年間、親本人やその家族と接してきているので、状況等色々と口添えもしてくれますし、ケアマネージャーの意見はとても大きなウエイトを占めていて、判定基準の大きなポイントになっているのではないかと思っています。
ただ、担当ケアマネジャーによっては同席しない、または日程が合わないなどにより同席しないこともありますので、よく担当ケアマネージャーと相談の上決めてくださいね。
親本人の状態と家族の様々な状況に合った要介護認定が更新手続きによって決まるといいですね!
最後に、
この更新認定申請の手続きを終えて認定された結果に対して不服というか現状のサービスを維持していく上で、この結果では。。。。、という場合には『区分変更申請』という申請が可能となります。
私の母の場合、一年経って状態が少しずつ下降線をたどっているにもかかわらず、要介護度がかなり下がった(=軽くなった)結果となってしまいました。
今のサービスを維持していくためにも、また金銭面においてもこの新たな介護度では無理があると思ったので、『区分変更申請』を行いました。
私と同じような状況の人もいるかと思いますので、この『区分変更申請』については別記事でお知らせしたいと思います。
↓
『区分変更申請』についてはこちらのページをどうぞ!!
スポンサーリンク